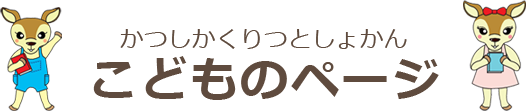2012年3月1日~4月30日に、図書館にあたらしく入った子どもの本の中で、 特 におすすめの本です。
子どもの読書に 関 する本もふくまれています。
本のタイトルのところから、 予約 することができます。
タイトルの 横 に、本の 種類 がわかるマークがついています。





ローセ・ラーゲルクランツ/作 エヴァ・エリクソン/絵 菱木晃子/訳
岩波書店
友だちがひとりもできなかったら、どうしよう。新しく1年生になったドゥンネはしんぱいです。でも、エッラ・フリーダとなかよしになってからは、なにをするにも毎日いっしょ。ドゥンネはとてもしあわせでした。ところが、エッラ・フリーダがとつぜんひっこしてしまい、ふたりはわかれわかれに。ないてばかりいたドゥンネですが…。
谷川俊太郎/文 長新太/絵
福音館書店
ずっとまえ、わたしはおかあさんのおなかにいた。でもいま、わたしはわたし。おかあさんも、おとうさんも、なくなったおばあちゃんも、あなたのひとり。あなたはいっぱいいる。でも、いまわたしとむきあうあなたはひとり。わたしがひとりしかいないように、あなたもひとりしかいない。
小林一夫/文 国際おりがみ協会/監修
文溪堂
子どもから大人まで、いろいろな国の人たちが楽しんでいる折り紙。世界に広がる折り紙や日本の折り紙をカラー写真で紹介し、鶴・かぶと・金魚・ぴょんぴょんかえるなどの折り方を折り図イラストと写真で説明。折り紙の歴史についても解説します。
渡辺暢惠/著 小柳聡美/著 和田幸子/著 齋藤洋子/著
ミネルヴァ書房
小学校・中学校・高等学校の子どもたちと本との出会いを演出するブックトークのコツをわかりやすく解説し、実際に学校司書が実践したさまざまなテーマのシナリオを紹介する。
富安陽子/作 平澤朋子/絵
アリス館
原っぱにわすれられてしまったお人形の花代は、ある日、加奈ちゃんにひろわれました。加奈ちゃんと花代は、実はお話ができるんです。加奈ちゃんと花代は、東光寺の本堂の四天王や、名前のないお人形、児童公園の横にあるおかしの家にいた青い目のお人形に出会い…。
安藤“アン”誠起/著
誠文堂新光社
カブトムシやクワガタムシは、どんな場所に生息し、どんな過ごし方をしているのか。また、それぞれどうやって産まれてきて、どれくらい生きるのか。カブトムシとクワガタムシの生態をはじめ、体のしくみ、つかまえ方や飼い方、種類の見分け方や標本の作り方などを、写真をたくさん使ってわかりやすく紹介。
エスター・アベリル/作・絵 松岡享子/共訳 張替惠子/共訳
福音館書店
ちいさなくろネコのジェニーは、にわで、しろとくろのネコ・チェッカーズと、そのきょうだいのトラネコ・エドワードにであいました。ジェニーは、おなかをすかせたかれらを、うちにおいてくれるようにキャプテンにたのみました。こうしてジェニーにあたらしいきょうだいができて、いっしょにすむようになりましたが…。
「黒ネコジェニーのおはなし」の最新作です。
ディック・ブルーナ/ぶんえ まつおかきょうこ/やく
福音館書店
くんくんはちゃいろのいぬです。あるひのこと、くんくんがあまりしずかなので、かいぬしのおばさんはしんぱいになって、くんくんをおいしゃさまへつれていきました。すると、くんくんにあかちゃんがうまれることがわかりました。それから9しゅうかんたった、あるまんげつのよる、おそくに…。
宮川ひろ/作 小泉るみ子/絵 童心社
3年生になった和人は、クラスの係をきめるとき、自分でかんがえて、黒板に「けんかとめ係」と書きました。すると先生が「けんかはとめるものではないぞ。しっかりとやらせるものだろう」というのです。先生のことばがよくわからない和人でしたが…。
梅原淳/著
誠文堂新光社
E5系・E6系、一番人気のN700系など、日本国内を走るすべての新幹線の車両と、線路や施設をはじめとする、さまざまなシステムを解説。そのほか、新幹線のさらに進化した形である超電導リニアや、新幹線にあえる場所も紹介します。
西村敏雄/作 福音館書店
「ぞうくん くうぞ よう くうよ ぞうくん ぱん くうぞ」「まさか さかさま かめ だめか」どうぶつたちのうんどうかいを、うえからよんでも、したからよんでもおなじ、さかさことばでかいています。うえからもしたからも、よんでみてください。
佐野藤右衛門/作
講談社
日本全国を飛び回り、きずついた桜の手当てをし、桜の新種をさがす佐野さんは、「桜守」とよばれています。桜のいのちを守るしごととは、いったいどんなものなのでしょうか?桜守のしごとを、写真とともに紹介します。
モリナガヨウ/作・絵
ポプラ社
電波塔ってなに?タワークレーンってどうやっておりてくるの?どんな人がつくっているの?634メートルの高さをほこる東京スカイツリーのひみつを、たくさんのイラストでくわしく紹介します。東京スカイツリーをさらに知るためのデータ、用語解説ものっています。
湯浅浩史/著
誠文堂新光社
奇妙な形の葉、おもしろい性質の葉、動く葉・巻きつく葉・へばりつく葉、地上でみられる根…。さまざまな環境に適応し、いろいろな形や大きさに進化した葉や根をもつ世界の植物を、たくさんの写真で紹介。アリと共生する植物、食虫植物ものっています。
えびなみつる/絵と文 渡部潤一/監修 中西昭雄/写真
旬報社
地球にもっともちかい、じぶんで光る星、太陽。地球にいのちのめぐみを与えてくれる、さまざまな顔をみせる天空のスター、太陽。そのほんとうのすがたを、ほんのすこしだけ科学的・天文学的な味方で、わかりやすく紹介する。
畑野栄三/文 全国郷土玩具館/監修
文溪堂
竹とんぼ、でんでん太鼓、竹馬、風車笛…。竹を使った日本の伝統的な竹細工のおもちゃを紹介。また、竹の性質や種類といった竹と竹細工に関する知識や、竹細工の歴史、水鉄砲やうぐいす笛など竹のおもちゃの作り方も説明します。
竹内龍人/著 誠文堂新光社
「だまし絵」とは、目の錯覚を活かした絵のことです。見る人がうっかりだまされてしまうような絵や写真をたくさん紹介。だまし絵を見るとき、目や脳がどうなっているのか、なぜだまされてしまうのかも解説します。
ライアン・アン・ハンター/文 エドワード・ミラー/絵 青山南/訳
ほるぷ出版
モグラは、トンネルをほります。アリは、トンネルをつなげて迷路をつくります。人間がさいしょにほったトンネルは、水のためでした。いまでは、ひとも、ひとが必要なものも、車やトラックやバスや汽車も、トンネルをくぐっています。せかいには、どんなトンネルがあり、どうやってほるのかをわかりやすくおしえます。
佐藤雅彦/作 ユーフラテス/作
福音館書店
きでできたいすには、たくさんのくぎがつかわれている。なんぼんささっているか、そうぞうしてみよ。こたえは、「エックスせんしゃしん」というぎじゅつをつかった、ものの中がすけてみえるしゃしんでわかる。ぜんぶで、20ぽんのくぎがつかわれていたよ。ほかにも、はりやまやちょきんばこなど、いろんなものの中をそうぞうしてみよ。
ジュール・ヴェルヌ/作 私市保彦/訳
岩波書店
休暇で6週間の航海に出るはずだった寄宿学校の生徒たち。ところが船が流され、嵐のはてに無人島に漂着してしまう。少年たちは力をあわせて、島での生活をきずきあげていく。「十五少年漂流記」としてしられる冒険小説を完訳。
ジュール・ヴェルヌ/作 私市保彦/訳
岩波書店
さまざまな困難にもめげず、無人島の生活を充実させていく少年たち。だが、島に悪漢が上陸し、ドニファンに危機がせまる。少年たちは、無事に故郷に帰ることができるのか? 「十五少年漂流記」としてしられる冒険小説を完訳。
レオ・レオニ/作 谷川俊太郎/訳 好学社
はまべにある、たくさんのいし。ふつうのいしがおおいけど、さかなのかたちをしたいし、がちょうみたいないし、かずをおしえてくれるいし、すてきなかおのいしなど、みたこともない、ふしぎないしもあって…。えんぴつでこまかくえがかれたいしがいっぱいの、たのしいえほん。
1979
年刊の
再刊です。
ルーネル・ヨンソン/作 エーヴェット・カールソン/絵 石渡利康/訳
評論社
ともだちをたすけるためにブルガリアへやってきたビッケとフラーケのバイキングたち。ところが、バイキングたちはみんな、絶望的になっています。なぜなら、ブルドゥース人がせめてきたからです。おこりっぽくて、戦いがだいすきな野蛮な敵…。ビッケとバイキングたちはどうなるのでしょうか?
1979
年刊の
再刊です。(バイキングのビッケシリーズ 4)
ルーネル・ヨンソン/作 エーヴェット・カールソン/絵 石渡利康/訳
評論社
フラーケのバイキング船が、あたらしい町にたどりつきました。ところが、この町は貧富の差がとてもおおきかったのです。王さまたちの圧政にはらをたてたビッケたちは、この町に正義を教えなければと、反乱をおこすことにしました。そして、ビッケはとびっきりの計画を思いつき…。
日本初刊行です。(バイキングのビッケシリーズ
最終巻)
デレック・ジュベール/著 ビバリー・ジュベール/著 小宮輝之/監修
ほるぷ出版
長年アフリカにくらし、野生動物のすがたを間近に観察してきた夫婦が、はずかしがりやで、めだつのをきらうヒョウの生活、獲物をとらえる様子、子そだてなどを、おおきな写真とともに紹介します。
わたなべゆういち/作・絵
佼成出版社
クジラのこ、ボンは、こおりのうかぶつめたいうみがすきでした。ひょうざんのまわりでペンギンたちとあそんでいると、おおきなこおりのかたまりがういてきて、ゆうらんせんをもちあげてしまいました。ボンとクジラのなかまたちは、のっているひとたちをたすけることができるでしょうか?
ふうせんクジラシリーズ
第2
巻です。
石橋真樹子/さく
福音館書店
フェリーターミナルのいちにちが、はじまります。きょうはじめて、とうちゃくするフェリーがやってきました。ゆっくりときしにちかづいてきます。おひるになると、おおがたフェリーがみえはじめました。ターミナルでは、にもつをはこびだすトレーラーヘッドや、ごみしゅうしゅうしゃがまっています。おおがたフェリーがきしにつながれると…。
市川里美/作
BL出版
きしゃが、ちゅうおうえきにはいりまあす、シュッシュッポッポー!おきゃくさんは、カモさん、ひつじさん、おさるさん、くまさんです。いすのあいだをぬけ、ソファにのぼって、さいごのおきゃくさんがおりました。きしゃがほっとしていると、おや、まだだれかのっていて…。
こしみずまさみ/へん
農山漁村文化協会
野菜の収穫がすくない冬の季節にそなえて、野菜を干したり、塩に漬けたりしたのが、野菜の保存食のはじまり。きりぼし大根、きゅうりの塩漬け、葉とうがらしのつくだ煮など、野菜のさまざまな保存方法とその作りかたを、イラストでわかりやすく説明します。
(つくってあそぼう 36)
こしみずまさみ/へん
農山漁村文化協会
くだものの保存の原理とさまざまな保存方法をイラストでわかりやすく紹介。いちじくのドライフルーツ、ぶどうのジャム、洋梨のシロップ漬けなど、実際のつくりかたや食べかたも収録。
(つくってあそぼう 37)
こしみずまさみ/へん
農山漁村文化協会
米・麦・豆はだいじな栄養素であるデンプンをたくさんふくんでいて、手間をかけなくても長く保存できます。いも類も保存しやすい大事な食料です。焼き米、あられ、きな粉など、米・麦・豆・いものさまざまな保存方法とその作り方を、イラストでわかりやすく説明します。
(つくってあそぼう 38)
こしみずまさみ/へん
農山漁村文化協会
栄養がおおい分、くさりやすい食材である家畜の乳や肉を保存するために、人間は水分をへらしたり塩をつかったりして工夫してきました。チーズやヨーグルト、バター、干し肉、ハムやベーコン、ソーセージなど、乳・肉のさまざまな保存方法とその作り方を、イラストでわかりやすく説明します。
(つくってあそぼう 39)
こしみずまさみ/へん
農山漁村文化協会
海にかこまれた島国・日本。おおむかしから人びとは海の豊かな幸を利用してくらしてきました。しめさば、でんぶ、かまぼこ、アンチョビなど、魚介のさまざまな保存方法とその作り方を、イラストでわかりやすく説明します。
(つくってあそぼう 40)
ディック・ブルーナ/ぶんえ まつおかきょうこ/やく
福音館書店
みどりのしばふのまんなかにいる、まるいまっかなりんごぼうや。じぶんには、あしもはねもないからどこにもいけない、とかなしそうなぼうやをじっとみていた、とうのうえのかざみどりは、みんながねむったよるおそく、そらをとんでやってきて、ぼうやをのせてとびたち…。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()